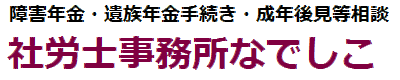遺族基礎年金・遺族厚生年金受給要件
1. 国民年金の夫又は妻が亡くなった時の遺族基礎年金
a.b.ともあくまで生計維持している18歳年度末(障害者20歳)までの子がいることが条件です。子のみの場合も対象です。
- 国民年金加入中や保険料を25年以上(納付+免除)納めた方が亡くなったとき。
- 国民年金加入中の場合は、死亡日の前日において前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上保険料を納めていること、又は死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
遺族基礎年金が受給できる可能性あり
しかし、18歳(障害者20歳)未満の子がいない方は
死亡一時金又は寡婦年金(妻60歳~65歳)を検討します。
2. 遺族基礎年金の額(令和5年4月、新規裁定者)
| 基本年金額 | 加算額 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 子1人 | 795,000円 | 228,700円 | 1,023,700円 |
| 子2人 | 795,000円 | 457,400円 | 1,252,400円 |
| 基本年金額 | 加算額 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 子1人 | 795,000円 | ・・・・・ | 795,000円 |
| 子2人 | 795,000円 | 228,700円 | 1,023,700円 |
*子3人目以降の加算額は、76,200円
3. 厚生年金加入した方がなくなった時の遺族厚生年金
- 厚生年金加入中の方が亡くなったとき
- 傷病退職し、その傷病の初診日から5年以内にその傷病が原因で亡くなったとき
- 障害厚生(共済)年金1級又は2級受給者の方が亡くなったとき
(その傷病が原因の死亡で障害認定日に3級だった方も可能性あり) - 老齢厚生年金・退職共済年金を受給中の方又は、受給権者で受給資格期間が25年以上ある方が亡くなったとき
a.b.の方は保険料納付要件を確認します
遺族厚生年金を受給できる人とは
支給順位で最上位者のみ受給権が発生します
第1順位 配偶者、子
第2順位 父母
第3順位 孫
第4順位 祖父母
*子、孫は18歳年度末まで(障害者20歳未満)
*夫・父母・祖父母は55歳以上(支給は60歳から)
*子のない30歳未満の妻は5年間の限定支給
*遺族年金の受給権者が再婚、死亡などすると失権し、次順位の方への転給はありません。
生計維持されていた方に限定されます
受給権のある方の年収が850万円未満であること、一緒に生活していた、仕送りしていたなど生計維持していたことが必要です。
4. 遺族厚生年金の額(令和5年4月)
a+bの額(亡くなった方のこれまでの給料や賞与の額で計算されます)
- H15/3まで平均標準報酬月額×7.125/1000×月数×3/4
- H15/4以降平均標準報酬額×5.481/1000×月数×3/4
- 老齢厚生年金受給中や受給権のある方の死亡は、亡くなった方の生年月日により乗率が変わります。
- 合計300月に満たない方は300月みなしで計算されるケースもあります。
- 中高齢寡婦加算(596,300円)が受給できる妻もいます。
- 平成27年9月以前に共済年金に加入していた方は、経過的職域加算が受給できる方もいます。
5. ご本人の年金が受給できるときは調整されます
<遺族基礎・遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給権のある方>
60歳~64歳
- 遺族基礎・遺族厚生年金又はご本人の老齢厚生年金のいずれか1つ選択受給となります。
65歳以上
- 老齢基礎・遺族厚生年金はご本人のものを受け取ります。
- 遺族厚生年金は、ご本人の老齢厚生年金との差額受給となります。
- 遺族厚生年金の計算方法が変わったり、中高齢寡婦加算を受給していた方は、経過的寡婦加算に代わり、減額される方や年齢から加算がつかない方もいます。
<障害基礎・障害厚生年金の受給権もある方>
60歳~64歳
- 1人1年金のため選択受給となります。
60歳~64歳
- 障害基礎年金を選択した場合、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金(経過的加算停止)の中から選択受給となります。
年金はこのように複雑です。どうぞお問い合わせください。
●遺族年金相談については、遺族年金相談ページをご覧ください。